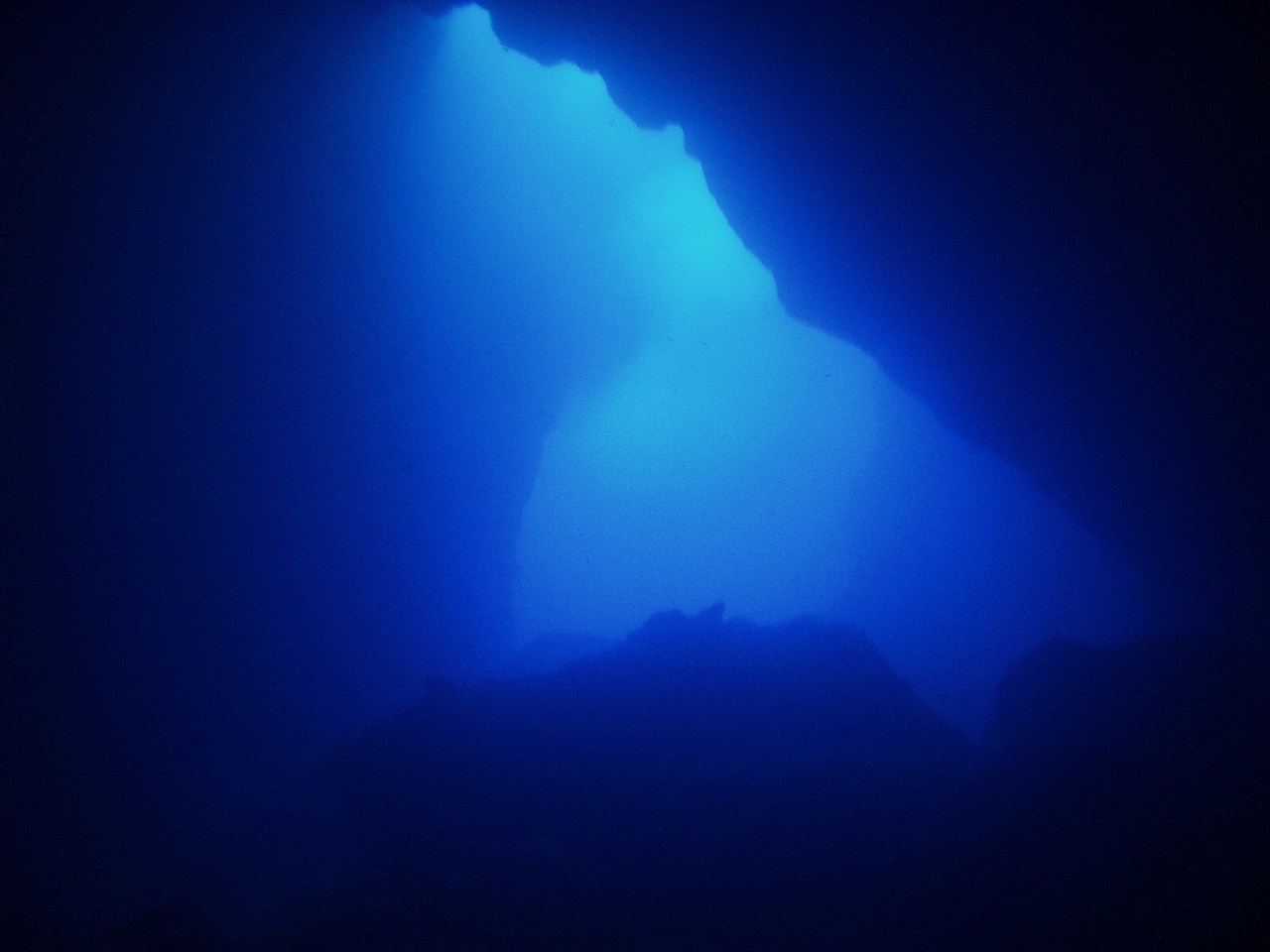今日は遺言書の検認で、関東圏の某家庭裁判所に行きました。
といっても、申立書は私が作成しましたが、司法書士はこの手続きの代理はできないので、今日の役割は依頼者さん(申立人)の付き添いです。
検認というのは、遺言を書いた人の相続人が裁判所に集まり、皆の前で遺言書を開封して形式面をチェックし、偽造や改ざんを防止するというものです。
遺言書の保管者や発見者である相続人は、速やかに申立をする義務がありますが、自筆の遺言が対象なので、公正証書遺言の場合は不要です。
今回、相続人調査(全員の戸籍の収集)にかなりの時間がかかりましたが、そのようなケースでは公正証書の方がよいかもしれませんね。
確実に相続手続きが実現できるという観点でも。
というのも、遺言書を提示しての相続登記や預貯金の解約は、検認済みの遺言書でないと受け付けてもらえないのですが、検認はあくまでも形式面の審査であって、遺言書が法的に有効か無効かを決めるわけではないので、このあとの各種の相続手続きが無事にできるかどうかは別の話なわけです。
今回、まずは相続登記の相談があり、検認の必要があるのでセットで依頼を受けたのですが、前述のように司法書士は代理人にはなれないので、検認単体で依頼がくることはあまりないんじゃないでしょうか。
私自身は2回目でしたが、前回は10年も前で、かつ、申立先(遺言者の最後の住所地の家裁)が中国地方の某県だったので、さすがに付き添いはせず、お一人で行っていただきました。
今回、相続人は全員欠席で、検認自体は極めてスムーズに終わり、予想よりもだいぶ早く事務所に戻れたため、相談登記も今日申請しました。
が、問題は遺言書の中身です。
法的要件は備えていますが、特定性の点では法務局から突っ込みが入る可能性が充分にあり。。。
昨年、弁護士さんからの依頼で申請した相続登記の遺言書よりは全然マシなので(そっちは無事に完了しました!)なんとかなってほしいところですが、管轄の法務局が違うと見解も違いますからね。。。
もしダメな場合は、思いを込めてせっかく書いた遺言書がなかったのと同じことになるので、別の手続きが必要になります・・・。
相続人間の関係が円満なら、面倒ではあっても遺産分割協議をすればいいのですが、代償分割といって、お金を渡す必要があるかもしれません。。。
良好でない場合は・・・。
遺言書自体はあるので、所有権確認訴訟ですかね。。。
もし法務局から指摘が入った場合でも簡単に引き下がるつもりはないですが、最後は何を言ってもダメなこともあるので(遺言は過去に事前照会をかけて、これじゃ登記できないよと言われたことが複数回あり・・・)何事もなく無事に完了することを祈る思いです。