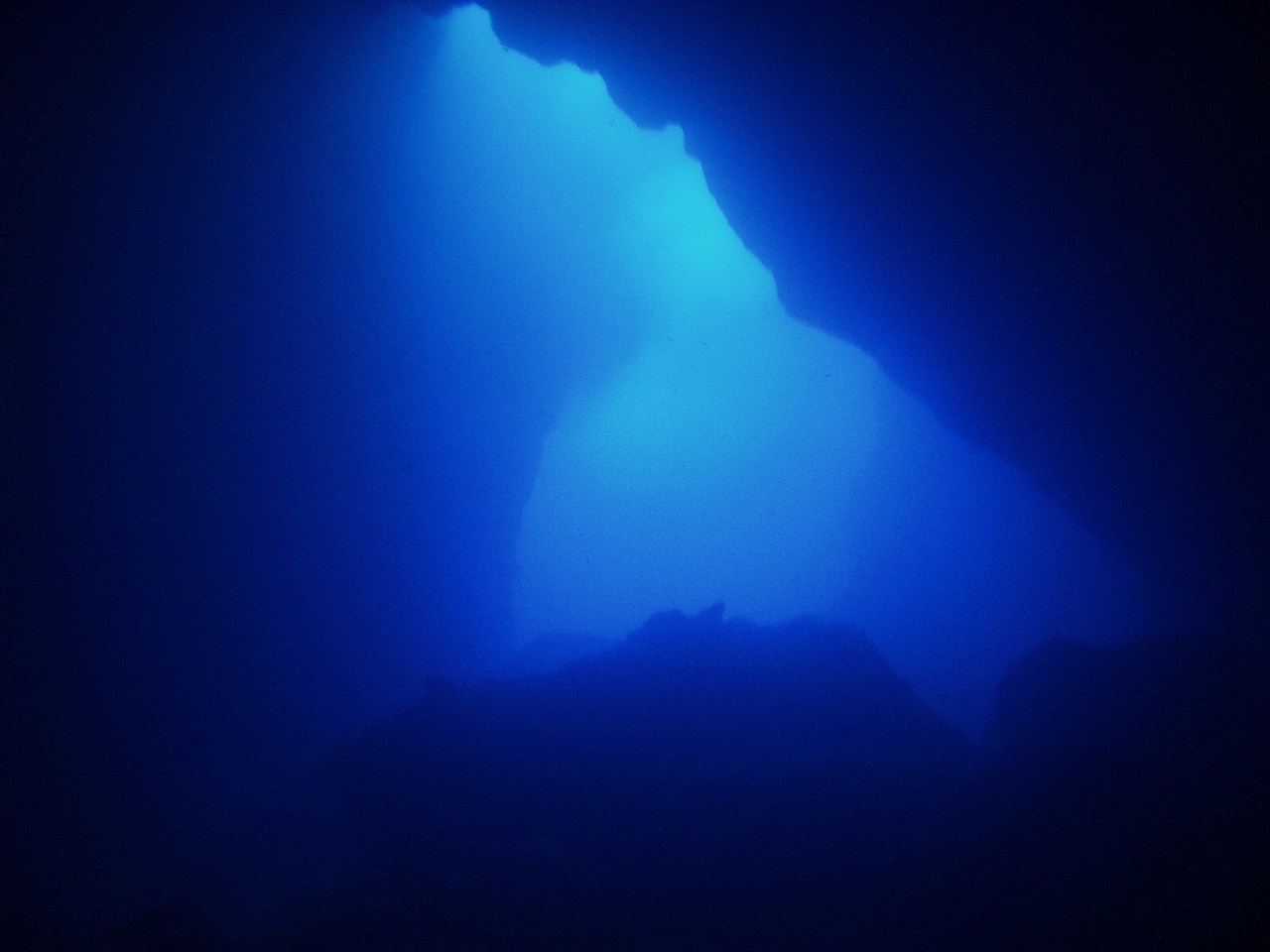今日は、二学期としては初めてことばの教室に行きました。
夏休み中は教室もお休みでした。
一学期の最後(7月8日)は、親との面談があり、普段は行っていない妻に行ってもらったため、私自身は6月以来だったので、かなり久々に感じました。
ことばの教室・小学校・家庭の三者間での情報共有のために連絡ノートに普段の様子や吃音の状態について書くのですが、野球の夏合宿のことを書くとともに、ここ2週間くらい(特にプロ野球のことを一生懸命話そうとするとき)ちょっとよくないと感じていたので、そのことを書きました。
しかし、学校に迎えに行ったあと教室に着くまでの会話では、それを感じず。
終わったあと先生からは、むしろ今までで一番いい状態かもと言われました。
それ自体は凄くいいことなのですが、本人にいろいろ聞いたところ、ゆっくり話すことを心掛けていると答えたらしく。
思い出したのは、一昨年zoomで参加した吃音交流会のこと。
講演をされた代表のお母さんの話では、吃音のお子さんが、凄く状態がいいと思った時期があり、よかった!と思ったら、実は本人の工夫によるもので、むしろかなりしんどかったようで。。。
ある程度の年齢になると、吃音に対する意識が随分変わってきて、喋ることに消極的になったり、どもりが出ない工夫をし始めることが考えられます。
後者は、それで本人の精神的な安定が保てるのなら、やむを得ないのかもしれませんね。。。
ただ、改善の手段として最初に出会った環境調整法の考え方は、そういった制限は一切かけるべきじゃないというものであり、微妙な気持ちになりました・・・。
直接法(話し方の工夫をすること)と環境調整法は、相対立するもので、両方平行して行うことはあり得ず、また、どっちがいいとも言えないのが悩ましいです(-_-;)
本人がいいと思う方法で、遠慮なく会話ができるのが一番ですけどね。